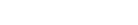※この記事は、「Sheetmetal メールマガジン」No.272(2025年9月30日配信)からの転載になります。
これまで大学医学部や理工系学部では、各教授の専門分野における責任を明確にすることで、その分野の教育研究を深く進める目的で「講座制」が導入され、教授を中心に、その専門分野に関連する教員や学生が集まり、研究室として活動するのが一般的だった。しかし、教授を頂点とするヒエラルキー構造により、若手研究者は教授の指導の下で研究を進めることになり、独自のアイデアや研究テーマを追求することが難しい状況が生まれていった。教授の意向に沿わない若手研究者の独立や独自の研究が困難となり、時には、「島流し」ともいわれるように学外の研究機関に異動させられる人事が行われることもあった。
その結果、若手の挑戦機会が制限され、教授の考えが研究の軸となりがちになるため、研究室内で新しい発想や異分野との連携が生まれにくくなり、研究全体の幅が狭まるだけでなく、急速に発展する新領域への対応が遅れる原因となり、日本の科学技術研究の生産性低下や他国との研究開発競争における遅れにつながる可能性が指摘されるようになった。
こうした現状に対応して文部科学省では、新たな教員組織のありかたが検討され、それぞれの大学の教育研究の目的に応じて、最適な体制が模索されている。
こうした中で先日訪問した北海道大学では、教育内容を整理し、教員組織を編成する基盤として「学科目制」を導入、学科目といった単位で教員が所属し、それぞれの専門分野における教育・研究を担う組織を導入する一方で、より自由な発想や手法で教育・研究を推進するために、学部・学科内に「研究所」を開設。具体的には、物理学・化学といった従来の基盤の学問のみならず、たとえば、生体の構造・機能の利用または模倣、最先端の量子フォトニクス、ナノテクノロジーの導入、さらには数理的解析の利用などの新しい手法を用いて研究を行うようになっている。
専門分野にとどまらず、研究所内のほかの研究室や他大学の研究室と連携して研究を推進することで新しい「発明・発見」、産業分野への「応用」を進めるため、教員の処遇もパーマネントではなく、5年、10年といった期限付きで採用、「成果」を重視した取り組みを行っていた。民間企業における「ジョブ請け」といわれる雇用形態にちかいものになっている。
大学組織も教員採用から研究テーマの決定や研究方法、指導教員との関わり方などが多様化しており、必ずしも従来の形式に沿ったかたちだけではなくなっている。