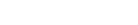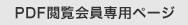紫式部に歴史を背負う姿を垣間見る
2008年のNHK大河ドラマ「篤姫」以来、大河ドラマファンとなり、その後は毎年楽しみにしている。ドラマは史実に基づくものの原作者や脚本家の主張が込められており、歴史的な背景の分析を含めて興味深い。特に「篤姫」の脚本家・田渕久美子氏による篤姫の母の「この世のものにはすべて役割があるのです。それは人とて同じこと」「人の命の重さに変わりはありませぬ。されど役割はおのずと変わります」という台詞―この「人にはそれぞれ役割がある」という言葉は、大きな支えになりました。
本年は「源氏物語」の作者・紫式部の生涯を描く「光る君へ」。脚本は大河ドラマ「功名が辻」を担当された大石静氏である。
「功名が辻」は山内一豊とその妻・千代の物語で、夫・一豊を支える「千代」が力強く描かれていた。女性特有の嗅覚と目線で時代を読み解き、潮目を読み、夫を叱咤激励して本懐を遂げるという筋立てがユニークだった。
その点では「光る君へ」でも、紫式部を通して平安時代の歴史の舞台裏での激しい権力闘争と、そこで翻弄されながら力強く生きる女性たちを描くという観点で興味深い。特に「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の かけたることも なしと思へば」という歌を詠み、政治の頂点に立った藤原道長との恋物語を通して描いているのが興味深い。
特に13話・14話で二人がそれぞれ自分の道を歩むまでのくだりは迫力があった。道長が父・藤原兼家に「父が目指す真の政(まつりごと)は何ですか」と尋ねると、「家の存続だ。民におもねるな」と諭される。「民のための政」を理想と考える道長は悩む。迷う道長に紫式部は「私は自分の道を進みます。私はあなたが信じる政をされるのを近くで見守っています」と言って立ち去る。話はそこから朝廷内の権力闘争へと展開、兼家の五男・道長が右大臣となって政の頂点に立って行く姿が描かれていく。脚本家・大石氏は史実を忠実に再現し、これからが楽しみだ。
それにしても平安時代の政権争いの中で政争の具となった女性の生き方には逞しさを感じる。これからの展開で、道長の推挙があって一条天皇の中宮なる道長の娘・彰子の漢文の先生、女房として勤めることになる紫式部。そして、彰子より前に一条天皇の中宮の座についていたのが定子。藤原道長の兄で関白だった藤原道隆の娘だが、父が急死し、実兄が後継争いで道長に敗れ失脚したことで、定子の立場も危うくなっていく。しかも定子の女房には清少納言がいた。二人が政争に巻き込まれることはなかったようだが、生きていくために時代を背負うこととなった女性の生きざまが、これからさらに描かれていくのだろう。
歴史の表舞台では常に男が主人公となっているが、実はそれを支え続けたのが女性たち。大石氏もおそらく紫式部を通して時代を支え、歴史を紡いできたのは女性たちだった、と言いたいのではないかと思う。「元始、女性は太陽であった」という言葉ではないが、女性の活躍なくしては歴史を重ねることはできなかったのではないか。
女性活躍社会とさかんに言われてきたが、平安の時代から女性たちは輝き、潮目を読みながら時代を支えてきた。百人一首に紫式部の歌「めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半(よは)の月かな」がある。歌人としての才能もあった紫式部は40代後半に亡くなったといわれている。タイムスリップして平安時代の女性たちの活躍を見るのも時代を読む参考になると思う。