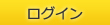日本のものづくり基盤を次世代につなぐ取り組みを推進
“企業の社会貢献”の枠組みを超え、社会全体の持続可能性に寄与する事業活動を行う
株式会社 アマダ 代表取締役会長 磯部 任 氏
 磯部任氏
磯部任氏
㈱アマダは1946年の創業以来、金属加工機械メーカーとして絶えず「創造」と「挑戦」を重ね、世界のものづくりを支えてきた。「お客さまとともに発展する」を経営理念の冒頭に掲げ、商品の販売からメンテナンスなどのサービスに至るまでみずから手がける「直販・直サービス体制」を国内外で展開してきた。これによって、お客さまが抱える課題を迅速に解決できるだけでなく、そこで得たニーズ・ウォンツを新たな商品・サービスの開発に生かし、次のソリューションにつなげていく ― こうした積み重ねがアマダ成長の源泉となっている。
産業界では今、地球温暖化による気候変動、労働人口の減少、熟練技能者の引退、若者の製造業離れ、脱炭素・デジタル化への対応、そしてコモディティー化に対応したグローバル競争の激化といった課題への対応が求められており、企業経営者には直面するこうした課題に真正面から取り組むことが求められている。
アマダの創業者・天田勇氏は、製造業の担い手を育てる「職業訓練法人アマダスクール」と、研究者・技術者を支援する「公益財団法人天田財団」を創設した。その活動は、単なる“企業の社会貢献”を超え、社会全体の持続可能性に寄与する重要な事業となっている。1978年に設立されたアマダスクールは2028年に創設50周年、1987年に設立された天田財団は2027年に創設40周年の節目をむかえる。こうした中で、2025年6月からこの2つの組織の理事長、代表理事理事長にアマダの磯部任代表取締役会長が就任した。
さらに、磯部会長は今年度から2年間、一般社団法人日本鍛圧機械工業会の会長にも選任された。直面する重要課題に対応して、“ものづくり大国・日本”を次の世代にも誇れる国として引き継ぐために、磯部会長が果たすべき責務は重い。
そこで磯部会長に、アマダグループとして社会貢献と経営の両立をどのように進めていこうと考えているか、率直な思いを語ってもらった。
構造的な課題に真正面から取り組む責任
― 2つの組織の理事長に就任された今の率直な気持ちと今後への抱負について、お聞かせください。
磯部任会長(以下、姓のみ) アマダグループのトップとして私は今、日本の産業界が直面する構造的な課題に真正面から取り組む責任を強く感じています。労働人口の減少、熟練技能者の引退、若者の製造業離れ、脱炭素・デジタル(DX、GX)への対応、グローバル競争の激化 ― これらは個別に対応すべき課題ではなく、複合的に解決すべきテーマです。
こうした時代に、製造業の担い手を育て、技術伝承をサポートする「アマダスクール」と、研究者・技術者を支援する「天田財団」の活動は、単なる“企業の社会貢献”を超え、社会全体の持続可能性に寄与する重要なものであると考えています。
私は2つの法人の理事長として、グループ全体の知見とリソースを最大限に生かし、「技術」「人」「社会」をつなぐ役割を果たしていきたい。アマダグループとしては、こうした公益活動を単独で行うのではなく、産業界・行政・教育機関とともに、日本のものづくり基盤を次世代につなぐ取り組みをしていきたいと考えています。
“ものづくり大国・日本”を次世代にも誇れる国として引き継ぐために、私は「社会価値の創出」を企業活動の中核に据え、社会貢献と経営の両立を力強く進めていきたい。
お客さまに必要とされる「教育」を目指して
― 金属加工機械専門の職業訓練法人であるアマダスクールの使命については、どのように考えていますか。
磯部 人材不足の状況を打開するためにお客さまは魅力ある企業づくりのため、労働環境や待遇の改善、女性も働きやすい職場環境の整備、キャリアパスの立案など人材確保に注力されています。
アマダスクールがお役に立てるのは人材育成の部分です。アマダスクールは認定職業訓練ができる機関として高度な教育を提供し、「職業人を育てる」使命を持っています。今後も初心者教育・安全特別教育・技能検定試験の準備講習など、お客さまの要望に沿って教育内容を拡充・強化していきたいと考えています。
アマダスクールが掲げるスローガン「学びの場から気づきの場へ」は、「学び」 ― 講義を一方的に進めても受講生にとっては受動的で頭に残らない、それよりもみずから疑問に「気づき」、納得がいくまで質問を繰り返して自分のものにする、自発的で双方向な講習を行うことを目指しています。
つづきは本誌2025年10月号でご購読下さい。