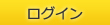クリーンなステンレス製品で社員や地域から愛される企業へ
社会貢献の取り組みに賛同した若手人材が続々入社
スエナミ工業 株式会社
 ファイバーレーザ複合マシンLC-2512C1AJ+ASR-2512NTK+ULS-2512NTK
ファイバーレーザ複合マシンLC-2512C1AJ+ASR-2512NTK+ULS-2512NTK
技術を継承しながら受注分野を拡大
 左から経営企画部の永田敏之さん、末次明社長、製造グループ長の林昌志さん
左から経営企画部の永田敏之さん、末次明社長、製造グループ長の林昌志さん
スエナミ工業㈱は末次明社長の祖父、末次武雄氏が1957年に創業した。末次武雄氏は農業の傍ら隣町の各務原市にある川崎重工業岐阜工場に勤め、航空機関連の板金仕事で技術を身に着け独立。創業後は川崎重工業から航空機部品などの板金部品を受託生産するようになった。
1960年頃からは末次社長の父親、末次正明氏が航空機部品加工で培った技術を民需にも活かそうと関市周辺の工場からさまざまなプレス加工や板金加工の仕事を受注するようになった。当時は、板金加工といっても大半はたたき板金で、タガネやハンマーなどの道具が活躍していた。航空機部品はレーザ加工のような熱加工を行うと切断面に変質層ができ、それが原因でマイクロクラックが入る。そのため、チタンなどの材料からコンターやはさみで板取りして、ポンチで穴をあけ曲げ線のケガキを入れ、そこにパンチを引っかけて曲げ加工するという手法で加工していた。そういった手板金の加工技術を継承しながら民生品、工作機械カバーなどの仕事を増やしていった。
手板金から機械板金への転換
1987年にはパンチングマシンARIES-245を導入した。しかし、近隣から騒音を指摘されたことから移転を考えるようになり、1993年に現在の場所に工場を建設・移転した。
1995年にはレーザマシンLC-1212αⅢ、1997年には板金ネットワークシステムASIS100PCLを導入してパンチングマシン、レーザマシンをネットワーク化し、デジタルなものづくりを推進。事務所で作成した加工データを呼び出せば誰が担当しても均一な製品ができる仕組みを構築していった。
 今年3月に完成したスエナミ工業㈱の新工場と本社事務棟
今年3月に完成したスエナミ工業㈱の新工場と本社事務棟 曲げ工程
曲げ工程
「お客さまの困っていることをやる」がモットー
末次明社長は「創業から65年、変わることなく『お客さまの困っていることをやる』をモットーに掲げ続け、創業当時に手がけた航空機部品の加工技術を昇華してさまざまな業界のお客さまと取引をしています」。
「リーマンショック以前は工作機械カバー、ブラケットの仕事が多かったのですが、リーマンショック後には受注が半減。景気変動を受けやすい工作機械の仕事から撤退して、食品加工機械、包装機械、繊維機械、農業機械、介護機器、薬品機械、焼却炉、塗装設備などに使用されるフレーム、カバー、ブラケットなどの板金加工品、製缶品、切削加工品を製作するようになりました」という。
 YAGレーザ溶接機YLW-400MT(奥)とファイバーレーザ溶接機FLW-1500MT(手前)
YAGレーザ溶接機YLW-400MT(奥)とファイバーレーザ溶接機FLW-1500MT(手前) 食品加工機械向けのステンレス板金筐体
食品加工機械向けのステンレス板金筐体
会社情報
- 会社名
- スエナミ工業 株式会社
- 代表取締役
- 末次 明
- 所在地
- 岐阜県関市側島286番地
- 電話
- 0575-28-6226
- 設立
- 1957年
- 従業員数
- 30名
- 主要事業
- 食品加工機械、建築部材、農業機械、薬品機械、焼却炉、一般金属部分のレーザ加工、板金加工、各種溶接、組立など
つづきは本誌2023年6月号でご購読下さい。