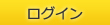ノーベル賞受賞でも喜べない科学技術研究の未来
2025年のノーベル賞の生理学・医学賞に大阪大学の坂口志文特任教授、化学賞に京都大学の北川進特別教授が選ばれた。
多くのメディアが日本の科学技術のレベルの高さが評価されたと報じていたが、受賞された研究者はいずれも70代。受賞理由となった研究は以前から行われてきたもので、30~40代の一線で活躍する研究者が世界的に見てどのレベルかをよく判断しなければならない。
その際によく引用されるのが、文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が発表する「科学技術指標」。これによると世界の科学論文数は一貫して増加しており、1981年比で2022年には5.3倍に増加した。特に2005年頃から増加ペースが加速している。
直近の「科学技術指標2025」によると、1年あたりの論文数(自然科学系・分数カウント法)は中国が59万9,435本で、シェアは29.1%。以下、米国の28万9,791本(14.1%)、インドの9万1,997本(4.5%)、ドイツの7万2,762本(3.5%)と続き、日本は7万225本(3.4%)で前年順位を維持した。しかし、注目度が最も高い「トップ1% 論文」数は12位、「トップ10% 論文」数は13位と低迷が続き、中国・米国とは大きく差がついている。
その要因の一つが日本の理工系博士課程への進学者数が、2003年をピークに長期的な減少傾向にあることだ。科学技術・学術政策研究所(NISTEP)によると、日本の大学院博士課程の入学者数は、2003年度の約1万8,200人をピークに減少が続き、2021年度には入学者数が1万4,300人台まで落ち込んだ。2022年度を境に増加に転じ、2024年度には約1万6,000人となった。ただし、この増加には社会人学生や外国人留学生の増加が寄与していると考えられている。
日本人の大学院博士課程の入学者数が減少する理由としては、博士課程の学費の自己負担割合が高いことに加え、生活費への不安がある。さらに博士号取得後のキャリアパスが不安定であることも大きな要因となっている。特に研究職として採用されても任期付きの不安定な雇用が多く、安定した常勤ポストに就くのが困難な「ポスドク」問題がある。さらに、修士課程修了者に対する求人が豊富にあるため、あえて不安を抱えて博士課程まで進むメリットを感じにくくなっていることもある。
また、大学部門の研究開発費のデータを見ると、2023年の日本(OECD 推計)は2.3兆円。各国の状況を見ると、米国は主要国の中で1位を維持しており、2023年は9.7兆円。中国は2012年に日本(OECD 推計)を上まわり、2023年では7.2兆円となっている。ドイツは2000年代後半から増加へ向かい、2016年に日本(OECD推計)を上まわり、2023年では2.9兆円となっている。
2000年を1とした場合の各国通貨による大学部門の研究開発費の指数(名目額)を見ると、2023年の日本(OECD推計)は1.0であり、伸びていないことがわかる。米国は3.4、ドイツは2.7、フランスは2.2である。
仕事でお会いする機会の多い大学研究者の多くがこうした状況を危惧されている。
しかし、最近は「自分がおもしろいと思ったアイデアに基づく研究をやりたい。指示されたテーマだけを追いかけていては研究の成果を出し、それを社会実装にまで持っていくことは難しい」と、グローバルに活躍される研究者も増えてきた。日本の科学技術研究の将来にも、ようやく光が差し込んできた。