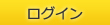不確実性が増す時代こそ、ニッチ市場への目配りを
板金業界の先行きへの不確実性が増している。
日本建設機械工業会は2月18日、2024年度の建設機械の出荷実績は前年度比11%減を見込むと発表した。2025年度についてもそのまま横ばいとなる予測だ。建設機械関連の板金サプライヤーは2023年度比で2割以上の受注落ち込みとなっており、この状況がしばらく続くことになる。
建設機械に続き板金の需要先として影響が大きい、工作機械業界の需要回復も遅れており、本格的な需要回復は秋口以降になると予想されている。
さらに、米国・トランプ大統領により4月から実施される貿易相手国と同水準まで関税率を上げる「相互関税」や、自動車など品目ごとの関税措置の導入による影響も懸念される。人手不足、円安、人件費の上昇、脱炭素対応など課題が多い経営環境の中で、経営のかじ取りが難しくなっている。
その一方で、ニッチな分野だが受注好調な業種も生まれている。
「構造不況業種」と言われ、きびしい時代が長く続いてきた造船業界はコロナ下に順風が吹き、新造船への注文が急増した。巣ごもり需要などで貨物の動きが世界的に活発になり、物を運ぶコンテナ船、バルクキャリア、LNGタンカーなどが不足、新造船への注文が急増した。アフターコロナでいったんその勢いはなくなったが、エネルギー価格の高騰、穀物不足などが影響していることもあって、海上荷動き量の増加などを背景に、2024年の新造船の受注量は2023年と比べて34%増加した(標準貨物船換算トン数ベース)。
日本船舶輸出組合が1月に発表した、国内造船所の2024年の輸出船契約実績(受注量)は、前年比7%減の1,116万総トン。1990年代は世界の造船市場の4割を占めていた日本の造船業界は、中国、韓国との激しい競争でシェアを落とし、最近は2割を割り込んでいる。それでも造船メーカーは3年以上の工事量を受注残として持つ一方で、5年先までの案件を抱えており、受注は好調だ。
船舶にはカバー・フレーム・架台・ブラケット・金具などをはじめとして、各種の製缶板金加工品が使われるとともに、舶用電機機器、舶用ボイラー、舶上焼却炉、舶用造水機などを舶用機器メーカーが製造・供給しており、ここにも多くの板金部材が使われている。
舶用電機機器の板金を受注する企業によると、大型のコンテナ船、バルクキャリアには、船内に電気を配線する「ケーブルトレイ」だけでも1隻につき、40~50トンの需要があるという。加えて中継器、配電盤などの板金製品が必要になる。この企業も造船メーカー同様に、2~3年先までの受注残があるという。
また、この冬の豪雪で忙しくなっているのが除雪に欠かせない除雪機・除雪車。今年の豪雪には間に合わないが、来年以降の豪雪対策として、関連メーカーは2025年度分の生産を大幅に増やした。すでにその生産は始まっており、関連する板金企業では増産対応に追われている。仕事量が薄くなっているだけに好調さが目立っている。
農業機械関連では農業人口の減少、農作業従事者の高齢化で農家戸数が大幅に減少しているが、耕作地を大規模化、営農集団による機械化農業が進んでいる。そのため、農業機械も大型化して、必要な板金部材が大型化、対応できる板金サプライヤーが不足しており、対応できるサプライヤーに仕事が集約され、繁忙な企業もある。
不確実な時代だからこそ、ニッチな分野の景況感もしっかりとウォッチすることが求められている。