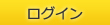鉄鋼生産のプロセスで生じる“皮膜”の熱物性を解明し、CO2削減に貢献する
芝浦工業大学 工学部 材料工学科 遠藤 理恵 准教授
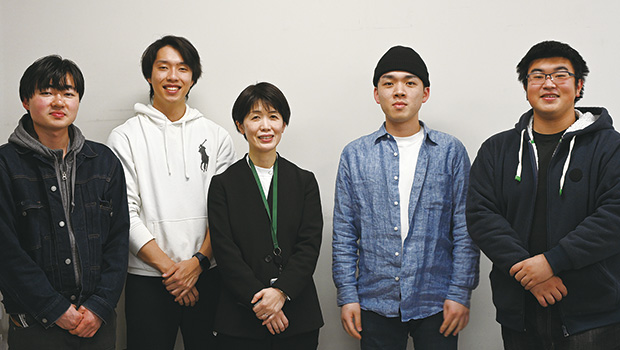 遠藤理恵准教授(中央)と「高温物理化学研究室」の院生・学生
遠藤理恵准教授(中央)と「高温物理化学研究室」の院生・学生
“邪魔者扱い”だった酸化スケールを味方につける
芝浦工業大学 工学部 材料工学科の遠藤理恵准教授の研究テーマ「酸化スケールの熱伝導率決定のため固体用表面加熱・表面検出レーザフラッシュ装置の開発」が、天田財団の2023年度「一般研究開発助成」に塑性加工分野で採択された。
遠藤准教授は自身が担当する「高温物理化学研究室」のメンバーとともに、製鉄所内の熱間圧延工程に着目し、熱物性と伝熱の観点から、温室効果ガスの削減に寄与できる研究を進めてきた。鋼の熱間圧延は800~1200℃もの高温で行われている。加熱や圧延の工程では、高温の鋼が空気中の酸素と反応して、鋼の表面に厚さ数十㎛の酸化スケール(皮膜)が生成される。酸化スケールが付着したまま圧延を行うと、製品の表面に疵が生じる原因になる。そこで製鉄所では高圧水などを使ってスケールを除去している。ただし、機械部品やビルの材料などに用いられる炭素鋼の生産現場では、水で除去してもすぐに鋼が再酸化し、常に製品の表面に付着している状態となる。酸化スケールはいわば“邪魔者扱い”だった。
「仕上げ圧延後の工程では、900℃に近い高温の鋼に水をかけ、500~400℃まで冷却が施されます。この工程では鋼の相変態※2もともないますから、温度制御がとても重要になります。高温では冷却水と鋼の間には水蒸気があって、比較的ゆっくりと冷やされます。その後、300℃あたりまで鋼表面の温度が下がると鋼と水が直接接触して(この温度を『クエンチ点』と呼ぶ)、そこから先は冷却速度が急速にアップすることが、過去の実験で明らかになっています。鋼の表面には実際には酸化スケールがあって、酸化スケールの特性でクエンチ点が変わってきます。つまり、“邪魔者”だと思っていた酸化スケールの特性をうまく利用して熱を制御すれば、鉄鋼製造で消費されるエネルギーやCO2排出量の削減に貢献できる可能性があるのです」(遠藤准教授)。
こうした認識は近年、製鋼分野の研究者の間で浸透しつつある。だが従来の熱物性研究は、室温でのデータ測定にとどまっていたり、実験値ではなく文献値を用いるなど、信頼性に欠ける面があった。遠藤准教授らは、こうした課題をクリアすべく、このたび世界で唯一となる、酸化スケールの熱物性に関する新しい測定方法を考案した。
つづきは本誌2024年10月号でご購読下さい。