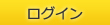人手不足・技術伝承が設備投資のトリガーに ― 技術開発に発想の転換が必要
『Sheetmetal ましん&そふと』編集主幹 石川 紀夫
熱心な来場者が増えた「MF-TOKYO」
7月16日から19日まで東京ビッグサイトで、「MF-TOKYO 2025」が開催され、来場者は3万1,207名となった。鍛圧機械(プレス・板金・フォーミング・自動化・周辺機器)の国際展示会として、2009年から開催されるようになったMF-TOKYOは、ドイツと並び世界で製造産業をけん引する日本の最先端の機械や技術を紹介し、日本の鍛圧機械産業の発展を目的として奇数年に開催されている。詳細なレポートは今号に掲載されているので、そちらを参照していただきたい。
私は最終日の19日に会場を訪れた。通常より1時間早い16時に閉幕することもあって、訪れる来場者も平日と比較すると少なかった。それでも会場内のブースでは、来場者が出展者と熱心な質疑を行っていた。最終日には、主催者による就活生を対象にした来場用バスが運行されたこともあって、会場内には学生の姿が目立った。会場内に設けられた大学研究室の出展ブースにも多くの学生が集まっていた。
出展者に話を聞くと、前回と比べてブースを訪れた来場者数は増加傾向で「有力な商談も増えた」とする回答が多かった。中には会場で契約した企業名をブース内に掲示する出展者も見られ、相対的に熱心なお客さまが多かったという。
コモディティー化したファイバーレーザ溶接機
とりわけ今回の展示会で目立ったのが、ハンディファイバーレーザ溶接機の出展数の多さだ。特に中国製のファイバーレーザ発振器を搭載したハンディ溶接機が20社以上から出展された。出力1500Wクラスで中国製の場合、250万円から購入できることもあって、会場で契約された来場者も多かったようだ。
板金工程で、最後のボトルネックなのが溶接工程。特にステンレスやアルミといった非鉄材料を使った医療機器、食品機械・厨房機器、理化学機器などでは、溶接条件やひずみ、溶接ビード面の仕上がりについてきびしい品質チェックがあるため、従来のTIG溶接では作業者のスキルが要求されていた。しかし、そうした腕の良い作業者を育成するためには最低でも5〜6年かかると言われている。
一方で、溶接作業はいわゆる「きつい・汚い・危険」と呼ばれる3K作業で作業者 ― 特に若手人材からは好まれていなかった。ただでさえ人手不足が慢性化する中で溶接作業者を確保・育成するのが困難な状況になっていた。
ファイバーレーザ溶接機は、入社間もない作業者でも操作を教えてもらい、溶接条件を設定すれば、すぐに熟練作業者と同じような品質の溶接ができるメリットがある。しかも、ファイバーレーザというハイテク技術とデジタル技術を活用できる点が若い人材へのアピールポイントとなるため経営者からすると、これまでのTIG溶接からの置き換えとして最適なツールとなる。しかもそれが250万円程度で購入できるとなれば、人手不足と溶接作業者の育成という課題の解決につながる期待から、急速に普及が進んだと考えられる。
もちろん、失明や火傷などの事故につながる作業だけに、安全教育の徹底とともに、ファイバーレーザ溶接機本体の安全機構の確認など、安全衛生への対応が十分かどうか確認する必要はある。いずれにしても、ハンディタイプのファイバーレーザ溶接機の普及が目立った。
つづきは本誌2025年9月号でご購読下さい。