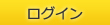モノづくりの"見える化"を図る生産管理システムの現状
受注形態の多様化・競争激化の中、WILLによる生産管理は必須
「生産の中心を司るシステムであってほしい」
サンケン工業 株式会社
 サンケン工業㈱の生産管理部門。1999年に導入した生産管理システムWILL受注・出荷モジュール+Mを使い、多品種少量・短納期の生産手配をかけていく
サンケン工業㈱の生産管理部門。1999年に導入した生産管理システムWILL受注・出荷モジュール+Mを使い、多品種少量・短納期の生産手配をかけていく
塗装までの一貫受注に対応
1985年、長野市内において竪岩惠行(たていわしげゆき)社長がサンケン工業(株)を設立。1987年には現住所に新工場を完成・移転し、同年、第2工場を完成しパンチングマシンCOMA-557の自動化ラインを導入した。1988年、一部2階建ての第3工場を完成、1992年に第4工場を完成し、自動倉庫MARS(10段9列)を設備。1997年には八幡工場が完成した。
1999年に生産管理システムWILL受注・出荷モジュール+Mを導入。2001年、パンチ・レーザ複合マシンAPELIO-357Vを導入するとともに、塗装事業を開始し、一貫受注体制を構築した。
2008年、本社工場にパンチ・レーザ複合マシンEML-3610NTP、レーザマシンLC-3015F1NT、ベンディングマシンHDS-1303NTと曲げ加工データ作成全自動CAM Dr.ABE_Bendを導入。ブランク工程の長時間連続稼働と、曲げ加工の外段取り化による稼働率改善を推進した。
さらに、ブランク・曲げ工程のネットワーク対応マシンの稼働状態をリアルタイムに管理することで、生産の”見える化”に取り組んだ。WILLの進捗端末からの手入力と、稼働サポートシステムvFactoryで収集されるネットワーク対応マシンの稼働データを活用し、より精度の高い生産管理システムを構築するため、生産管理事務所を増築した。
 代表取締役の竪岩惠行氏(左)、生産管理課の祢津洋子課長(右)
代表取締役の竪岩惠行氏(左)、生産管理課の祢津洋子課長(右)
建設機械関連が60~70%
最新鋭の設備による効率化と生産の”見える化”によって、作業者の勘や経験に頼ることで発生しがちだった”ムダ・ムラ・ムリ”をなくす”3ム主義”を踏襲することができるようになっていった。
同社の顧客台帳に登録された得意先は、毎月発注のあるところ、年数回の発注しかないところまで含め、約130社。このうち主要な得意先はミニショベルや高所作業車、カーゴクレーン、クローラークレーンなどを製造する建設機械メーカー4社。そのうち3社は長野県内に本社工場があり、ミニショベルの燃料用・作動油用のタンク、クレーンのブーム、高所作業車のカバー、フレーム、キャビンなどを受注する。これら3社からはサブモジュールをセット受注しており、月間生産台数も機種により50~100台単位で、板金加工、溶接組立、塗装までを一貫して対応している。残りの1社からはパーツ受注で、部品供給のみを行っている。
これら建設機械関連4社からの売上は、同社の売上全体の60~70%を占める。このほかに消音ボックスや特装車擬装品、一般産業機械、電子・電機機器部品なども手がけているが、多品種少量生産品が大半を占めている。
 2008年に導入したパンチ・レーザ複合マシンEML-3610NTP+RMP-48Mが自動倉庫MARSと連動する
2008年に導入したパンチ・レーザ複合マシンEML-3610NTP+RMP-48Mが自動倉庫MARSと連動する
つづきは本誌2014年12月号でご購読下さい。
タグ
- タグはまだ登録されていません。